【4】小笠原三代
寛永9(1632)年・・・
寛永9(1632)年10月28日、細川氏が加藤氏改易後の肥後54万石へ
寛文6(1666)年5月29日、長次死去し、広津の天仲寺山の墓所に葬られました。二代
享保元(1716)年、
■中津小笠原 略図
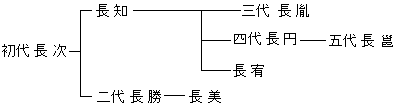
■小笠原長次の墓

町指定 史跡 昭和60年4月1日
広津 天仲寺山上
中津小笠原初代藩主の長次公は、寛文6(1666)年の5月29日、52歳で亡くなりました。長次公は遺言で「自分を葬るときは、鎧・甲を身につけ、腰には太刀、手にほっすを持たせ、広津山に埋めよ」と言って絶命したと伝えられています。墓前には、家臣たちから奉献された灯籠101基が参道一帯に建てられています。昭和48(1973)年に天仲寺の公園整備事業が行なわれ、長次公の墓も修復されました。地下2メートルほど掘り下げたところに石棺があり、遺言どおりの姿をした長次公が、中津城の方向を向いたように葬られているのが確認されています。
■小笠原長円の墓
 町指定 史跡 昭和60年4月1日
町指定 史跡 昭和60年4月1日
広津 天仲寺山上
中津小笠原三代藩主の長胤は、藩政が悪かったことから、元禄11(1698)年7月、幕府から中津8万石を没収され、小倉の配所に左遷されました。その翌日、幕府は特使をもって弟の長円を下毛・宇佐・上毛三郡のうち4万石に封じて中津城主としました。長円は身体が弱く、病気がちであったため、下毛郡東浜村に離亭をつくり、病気療養をしていましたが、正徳3(1713)年に病状が重くなり、長邕を跡継ぎにと遺言し、10月に38歳で亡くなりました。長円の墓は五輪塔墓標で、地輪正面に「真浄院殿義英宗高大居士」、右側に「正徳三葵巳」、左側に「十月十二日」と刻まれています。
■小笠原長美の墓
 町指定 史跡 昭和60年4月1日
町指定 史跡 昭和60年4月1日
広津 天仲寺山上
小笠原長美は、中津小笠原二代長勝の長男でありますが、家を継がずに、中津に在住していました。享保元(1716)年に、五代長邕が6歳で病死し、小笠原家に跡継ぎがいないため、幕府は領地を没収しました。長美も小倉領の築城郡八田村(現、築上町)に移住したが、享保2(1717)年9月20日に死去しました。小笠原家にゆかりのある天仲寺山に葬られました。墓標は笠付位牌形で正面に「浄徳院殿自覚宗観大居士」、右側「享保二丁酉年九月廿日」と刻まれています。
■小笠原長次公坐像

吉富フォーユー会館
この像は、領民や家臣たちに慕われつつも寛文6(1666)年の5月29日に死去した、小笠原長次公の遺徳を偲び、二代長勝公が作らせたものです。坐像は、像高15.4センチメートルで右手に笏を持ち、左手には太刀を持った束帯姿で畳に座っています。小さな木造ですが、本像・厨子ともに手慣れた上方仏師の作であると思われます。
■小笠原灯籠(とうろう)
 有形文化財 建造物
有形文化財 建造物
広津 天仲寺山上
中津小笠原初代藩主の長次公の一周忌の際に、家臣たちが奉献したもので、天仲寺山に101基が建てられ霊廟として整備し、長次公の功績を偲びました。時代の流れの中、燈籠は散逸し現在、2基の燈籠が墓前に戻り十数基の所在が確認されています。
■天仲寺の石盥盤(せっかんばん)
 町指定 史跡
町指定 史跡
平成4年11月16日 広津 天仲寺境内
石盥盤は社寺に参拝する前に手や口を清めるための水を溜めている手水石と同じ役割をもつものです。中津小笠原初代藩主の長次公は、寛文6(1666)年に亡くなりました。家臣たちは、長次公の一周忌にあたり、墓前から参道一帯に101基の灯籠を建て、霊廟として整備し、長次公の功績を偲びました。その際に、この石盥盤も奉献されました。
■小笠原長勝公奉納刀

有形文化財 工芸品
小犬丸 八幡古表神社
中津小笠原二代藩主の長勝公が、延宝9(元禄元年・1681)年、病気平癒祈願のため奉納したもので、刀、脇差ともに、領内の刀工に作らせたものです。その際には、大小数振の刀剣が作られ、耶馬渓の羅漢寺などにも奉納されたと伝えられています。
- 刀 - 長さ 2尺6寸5分
- 銘文-表 為武運長久神納之
小笠原信濃守長勝
裏 - 于時延宝九辛酉五月吉辰 - 豊前中津住 長利作之
- 脇差 - 長さ 1尺8寸3分
- 銘文 - 表 為武運長久神納之
裏 - 于時延宝九辛酉五月吉辰
豊前中津藩住 国吉作之
お問い合わせは教育委員会
教務課
電話0979-22-1944
〒871-0811 福岡県築上郡吉富町大字広津413番地1













