【7】美濃派の俳諧と地域文化
■美濃派俳人
日本俳諧史上で中興者の位相にあった俳聖松尾芭蕉は、
全国の俳壇は、都市系俳壇(京都・大坂・江戸の三都を舞台に活躍する貞門派・談林派)と地方系俳壇(美濃派・伊勢派)の2つに大別できます。都市系は、
支考の後は、仙台
そして、美濃派俳人としては、岸井の二松庵・西友枝の
近世中期以降の地方俳壇の隆盛は、美濃派や伊勢派の行脚俳人の諸国
吉富は、地方文化の醸成地であり、集束地でもあったのです。
■根来東麟の墓
 史跡 広津 天仲寺山東側
史跡 広津 天仲寺山東側
根来東麟は、享保6(1721)年に京都に生まれ、幼い頃より優秀で、医術を学び、多くの難病を治療しました。また、大変優れた人物として人望が高く、明和2(1765)年、45歳の時に中津藩主奥平公に招かれて侍医となりました。天明7(1787)年、67歳で亡くなるまで、東麟は医師として優れていただけでなく、多くの書も好み、医術と学徳は多くの人に慕われました。東麟の墓は、天仲寺山の東側にあり、位牌形の墓標の正面には「根来東麟墓」と隷書で刻し、その下には東麟の経歴と業績などの銘文が刻まれています。
■美濃派の句碑

町指定 史跡 昭和62年3月2日
広津 天仲寺境内
天仲寺境内に立ち並ぶ5基の碑は、俳聖松尾芭蕉や地元和井田の俳人澄月庵耘露坊、広津の俳人孤月庵松月坊など美濃派の俳人の功績を偲んで門人であった中津花中坊とその弟子の沙浪庵が建立したものです。美濃派というのは、蕉門十哲の1人で美濃国(岐阜県)の俳人各務支考が開いた俳諧の一派で、美濃・伊勢を拠点に活動していたため、そう呼ばれました。
■美濃派の句碑紹介
第一句碑 耘露坊 句碑
志ら志らと夜も明きって原の霜
第二句碑 芭蕉 句碑
ものいへば唇寒し秋の風
第三句碑
牛阿る声に鴨たつゆふべ哉 獅子庵人
住倦いた世とは嘘なり月よ花 黄鸝園
仰向いて分別はなしけふの月 帰童仙
つゝ立て杉こころなしけさの雪 雪炊庵
くもる程よい空奪ふ桜かな 朝暮園
ほろほろと雨の降り出す枯野哉 道元居
聞きまかふ物なし雲に郭公 以雪庵
第四句碑 孤月庵 句碑
飯煙の棚引くひまに梅白し
第五句碑 遅日庵 句碑
音ほどは松もこぼさずはつ時雨
■原田東岳の墓
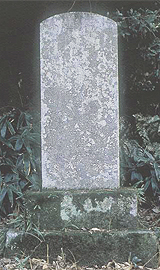 史跡 広津 広運寺境内
史跡 広津 広運寺境内
原田東岳は、中津奥平藩政時代の儒学者でした。東岳は享保14(1729)年に大分県日出に生まれ幼い頃から優秀で、日出藩主の木下俊泰は東岳を京都に遊学させ、さらに江戸で古文辞を学ばせました。東岳の名声は高く、小倉の増井玄覧と並び称される程でした。東岳の墓は広運寺境内にあり、墓標は位牌形で上部に隷書で「東岳原田先生墓」と刻し、その下に東岳の経歴と業績を紹介した銘文が刻されています。
■竹本津太夫の墓
 史跡 広津 天仲寺山東側
史跡 広津 天仲寺山東側
この竹本津太夫は、大阪文楽座の大立物で浄瑠璃の重鎮人間国宝の竹本津太夫の五代前にあたる人です。津太夫は、中津藩主奥平公に仕える客員(芸人)として招かれました。当時の中津城下町周辺では、浄瑠璃が盛んで、津太夫には多くの門人がおり、町内でも広津や小犬丸の商家を中心に広く普及したそうです。津太夫の墓は、自然石を使った墓標で「竹本津太夫」と刻まれています。
■島田虎之助修練の地
 史跡 広津 天仲寺公園
史跡 広津 天仲寺公園幕末の剣豪「島田虎之助」は、少年時代から剣の道に生きる決心は固く、昼は中津の剣術指南役堀一刀斎の道場、夜は天仲寺山に毎晩登り、一人剣法の修練に精進し、18歳のとき、九州各地を武者修行しました。修行中には、各地を巡りその名を轟かせていましたが、鍋島藩や柳川の大石道場での勝負で、自分の未熟さを悟り、筑前の仙崖和尚のもとで参禅し、心の修養と剣の修行に励み、中津に帰った後も天仲寺山で修練を積んだといわれています。天保18(1837)年に、江戸浅草の新堀に直新影流の道場を開きました。このときの門下生が、幕末から明治の政治家、勝海舟で、虎之助は海舟に大きな感化を及ぼしたと伝えられています。虎之助は、漢学の知識に加えて蘭学や西洋式軍事教訓にも造詣が深く、門下生にも学問の大切さを説きました。また、剣術の目標を「剣心一致」とし、精神の統一を強調しており、剣の才能は素晴らしく、「幕末の剣聖」と呼ばれました。
お問い合わせは教育委員会
教務課
電話0979-22-1944
〒871-0811 福岡県築上郡吉富町大字広津413番地1













