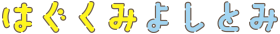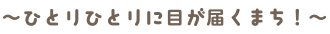食育について
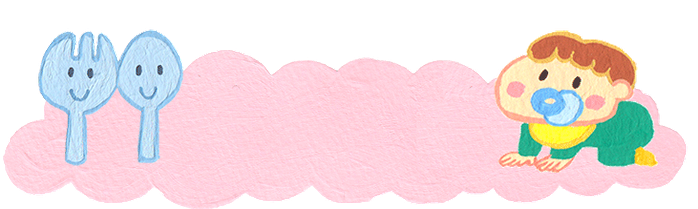
食育とは
食を通して「食べる力」=「生きる力」を育むことです。
朝食欠食、食生活の乱れなど、子どもたちの健康を取り巻く問題を解決する重要な役割を
朝食欠食、食生活の乱れなど、子どもたちの健康を取り巻く問題を解決する重要な役割を
果たすことができます。
~食育で育てたい「食べる力」~
(1)心と体の健康を維持できる
(2)食事の重要性や楽しさを理解する
(3)食べ物の選択や食事づくりができる
(4)一緒に食べたい人がいる(社会性)
(5)日本の食文化を理解し伝えることができる
(6)食べる物やつくる人への感謝の心
離乳期
「ごっくん・もぐもぐ・かみかみ・おいしい」を覚える。
手づかみ食べを経験し、少しずつスプーンやフォークを使って楽しく食べるようになります。
1歳
子どもの「食べたい!」という意欲を育てる時期。
1日3回の食事のリズムを覚えましょう。
2歳
いろいろな食材の味覚の幅を広げる時期。
旬の食材を取り入れて、いろいろな味や食材・食品の経験をさせてあげましょう。
3歳
食事のマナーを覚える時期。
お箸の使い方や基本的な食事の習慣・態度などを、毎日の食卓で、ゆっくり地道に育てていきましょう。
幼少期の味の経験は、大人になった時の食習慣に大きく影響するものです。
濃い味付けを好むようになると、生活習慣病などの病気につながりますので、早いうちから食育を意識して、家庭で取り組んでみましょう。






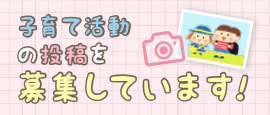





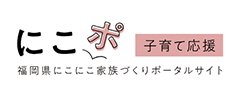




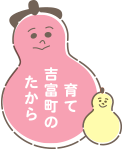

 スマホサイト
スマホサイト