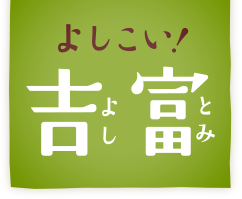広運寺(野田新助・吉岡八太夫の墓)
宇都宮家最期 奮戦の家臣
最後の地で静かに眠る
広津氏と広運寺

広津氏が史料として確認されるのは鎌倉時代末期、嘉暦(かりやく)3(1328)年、上毛郷司田部忠通(かみつみけのごうじたんべのただみち)が「ひろつの小太郎」と称せられていたことです。
田部氏は宇佐宮の役人として、その一族が宇佐郡・下毛郡でも勢力をもち、広津氏は宇佐宮領の上毛荘(かみつみけのしょうか)、上毛別符の田所という役人も務めていました。
山国川の河口の港に住み、物資の集散に関与していたこともあり、南北朝時代から室町時代には活動範囲は下毛郡から宇佐郡に及び、勢力を強めました。
15世紀、守護大名大内氏が豊前国で強大な力を示しはじめると、広津氏は大内氏の家来となって、上毛 郡代 (ぐんだい) や下毛郡 反銭奉行 (たんせんぶぎょう)として重要な役目を果たしました。
16世紀ごろ、大内氏が滅び、豊後の戦国大名大友宗麟(そうりん)が豊前に勢力を伸ばすと、広津氏は大友氏の家来となって、広津城に立籠たてこもり、秋月方の攻撃を撃退しました。
しかし、豊臣秀吉の命令を受けた黒田孝高が小倉に上陸する前の5年間は秋月氏に従いました。
黒田氏が中津城主となると、広津氏は、小倉城主となった毛利勝信の家臣となり、広津の地を離れました。関ヶ原の戦い後、浪人となっていた広津氏は黒田氏に招かれ、福岡城下に移り住むことになります。
広津氏の菩提寺と孝えられる広運寺(こううんじ)は、天文6年、大寧寺(だいねいじ)の助翁永扶(じょおうえいふ)によって曹洞宗(そうとうしゅう)の寺院として開かれました。
助翁はまもなく大内義隆に求められて田川郡上野あがのの天目山興国寺(てんもくざんこうごくじ)を中興しました。
また、宇都宮鎮房(しげふさが)、天正16年に豊臣秀吉の命令をうけた黒田長政によって、中津城で謀殺されたとき、広運寺で待っていた家臣16人は、これを知って、この寺で切腹したと伝えられています。
吉岡八太夫・野田新助の墓
天正16年、城井谷の城主・宇都宮鎮房(しげふさ)が中津城で黒田長政の策謀によって討たれました。
『城井谷きいだに物語』という本に、鎮房の家臣の吉岡八太夫(はちだゆう)と野田新助は奮戦し深手を負いながらも、山国川を渡り広運寺まで逃げ延びましたが、この地で自害となりました。
その2人の墓が今もあると「築上郡史」に記されています。
それがこの墓とされており、今も歴史を静かに物語っています。